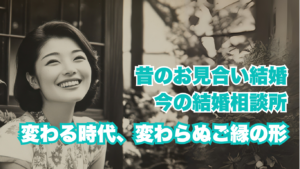明治時代の結婚観──家と家をつなぐ「結婚」
明治時代、日本の結婚はまだ「家制度」が色濃く反映されていました。
結婚は、個人の感情よりも家の存続や社会的地位**が重視され、いわば「家と家を結ぶ契約」。
本人同士が出会う前に、親や親族が相手を決めるのが一般的でした。
大正時代、恋愛の風が吹き始める
大正時代に入ると、都市部を中心に「恋愛結婚」という言葉が少しずつ浸透していきます。
背景には、女性の教育の普及や西洋文化の影響、そして雑誌や小説で描かれる恋愛ストーリーの広がりがありました。
とはいえ、まだ地方では政略結婚が主流で、恋愛結婚は「少し冒険的」と見られることも。
昭和初期、縁談広告が新聞・雑誌に登場
昭和初期になると、新聞や雑誌には「縁談広告」が登場します。
「〇〇家 長男、27歳、医師。見合い希望」
「東京在住、家柄良、20歳、女子高卒」
といった文章が並び、今でいう婚活サイトやマッチングアプリのような役割を果たしました。
現代婚活とのつながり
昔は親や仲人を通して、今はアプリや結婚相談所を通して──。
「出会いの形」は変わっても、安心できる相手と未来を築きたいという思いは、昔も今も同じです。
歴史を振り返ると、今の婚活スタイルがどれほど自由で、自分の意思を大切にできる時代なのかが見えてきます。
政略結婚から恋愛結婚へと移り変わった背景には、文化や価値観の変化がありました。
私たちが自由に相手を選べる今だからこそ、歴史を知り、自分らしい結婚観を持つことが大切です。